生活保護を受給している方が医療や介護サービスを利用する際には、医療券・介護券が必要です。しかし、現場では利用者本人が必ずしも自治体に連絡していないこともあり、訪問看護ステーション(訪看)が窓口となって対応することがあります。本記事では、訪問看護の立場から医療券・介護券の取得や確認の流れを解説します。
Contents
医療券の現場での扱い
生活保護受給者は、医療費の自己負担が原則ゼロになります。その際に必要となるのが医療券です。
- 発行元:自治体の福祉事務所(生活保護担当)
- 利用方法:病院や薬局に提示
現場での実態
訪問看護では、利用者様自身が医療券の発行手続きをしていないこともあります。その場合、訪看事業所が 福祉事務所に電話やメールで医療券の発行依頼 を行い、医療サービスが滞りなく提供できるように調整します。
介護券の現場での扱い
介護券は、生活保護受給者が介護保険サービスを利用する際に必要です。原則、利用者の自己負担はゼロです。
- 発行元:自治体の福祉事務所または介護保険担当課
- 利用方法:介護サービス事業所に提示
ケアマネとの連携が必須
介護券は、ケアマネジャーが作成した利用票が先に生活保護課に提出されていないと発行されません。そのため、訪問看護ステーションはケアマネジャーと連携し、介護券が発行されていない場合に福祉事務所へ確認や依頼を行います。
事業所が連絡すべきポイント
医療券
- 利用者が手続きをしていない場合は訪看が福祉事務所に依頼
- 医療券の提示により、訪問診療や薬の手配がスムーズに行える
介護券
- 利用票が福祉事務所に提出済みか確認
- 未発行の場合はケアマネと連携し、福祉事務所へ発行依頼
ポイント:訪問看護ステーションは、利用者本人の手続き不足を補う役割を担います。自治体とのやり取りや書類確認を行うことで、医療・介護サービスの滞りを防ぐことができます。
生活保護課の連絡先について
全国の生活保護課の連絡先をまとめた公式一覧はありませんが、以下の方法で確認できます。
1. 自治体の公式ウェブサイト
- Googleなどで「[自治体名] 生活保護 担当窓口」や「[自治体名] 福祉事務所 連絡先」と検索
- 例:東京都渋谷区の場合、「渋谷区 生活保護 担当窓口」で検索すると福祉事務所の連絡先が表示されます
2. 地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談
- 訪問看護ステーションは、地域包括支援センターやケアマネジャーと連携することで生活保護課の連絡先や手続き情報を確認可能
- 専門職と連携することで、適切な窓口への案内や調整がスムーズに行えます
訪問看護ステーションとしては、医療券・介護券の取得状況を把握し、必要に応じて自治体と連絡を取りながら利用者様がスムーズにサービスを受けられる体制を整えることが大切です。
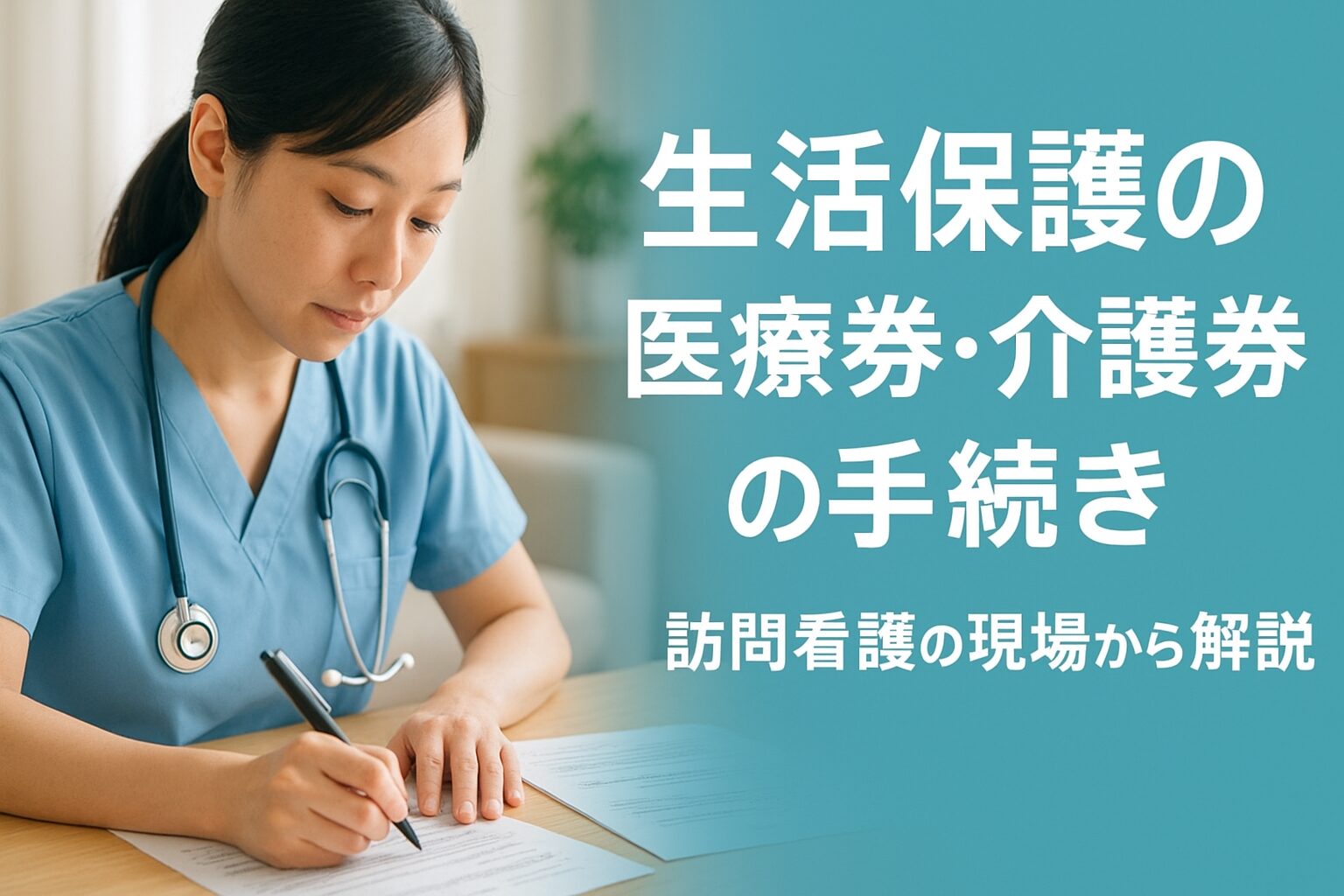
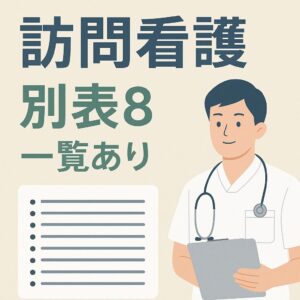




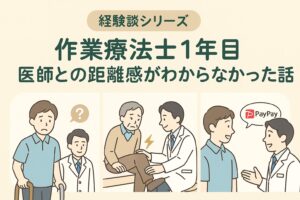

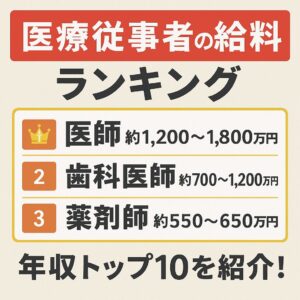
コメント