在宅療養を支えるサービスの一つに「訪問看護」があります。
病気や障害があっても自宅で生活を続けるために必要不可欠な支援ですが、利用にあたって費用負担や手続きは複雑です。
特に「医療券(医療依頼書)」が必要かどうかは、利用者の公費助成制度や生活保護の有無によって異なります。
今回は、医療券が不要な場合と、特定の助成制度を利用する場合の考え方を分かりやすく解説します。
Contents
💡 そもそも医療券とは?
医療券は、生活保護を受給している方が医療サービスを利用する際に、市区町村の福祉事務所が交付する書類です。
医療券を訪問看護ステーションに提出することで、利用者の自己負担分が公費(医療扶助)で支払われます。
生活保護を利用している場合、訪問看護を含む医療費は原則医療扶助でまかなわれるため、医療券が必要です。
✅ 生活保護は「最後のセーフティネット」
ここがとても大切なポイントです。
生活保護法には「他法他施策優先の原則」があります。
これは、生活保護が「すべての公的支援のうち最後の砦」と位置づけられているため、まず他の助成制度を優先的に使うことが原則です。
つまり、生活保護受給中であっても、次のような公費負担制度が利用できる場合はそちらを先に適用し、それでも自己負担が残る場合に医療扶助(医療券)で補います。
📝 医療券が不要なケースとは?
以下のような場合は、訪問看護の利用にあたって医療券を申請せずに済むことが多いです。
① 生活保護を受給していない場合
生活保護の医療扶助は使わないため、医療券は不要です。
医療保険(健康保険、後期高齢者医療など)の自己負担が発生します。
② 要介護認定を受けて介護保険で訪問看護を利用する場合
65歳以上で要介護認定を受けている方は、原則介護保険が優先されます。
この場合も医療券は不要です。
③ 医療保険で訪問看護を利用するが、特定の助成制度を利用する場合
ここが複雑で誤解されやすい部分です。
生活保護ではなく、下記のような**公費負担医療制度(受給者証)**を利用する場合は、医療券を発行せずに済むことがあります。
✅ 主な公費負担医療制度の例
以下の制度は、医療保険の自己負担を軽減する仕組みです。
📌 特定医療費(指定難病)助成制度
対象:
パーキンソン病、ALSなど国が指定する難病。
特徴:
- 医療保険の自己負担部分を公費で補助
- 所得に応じて月額負担上限が設定
- 訪問看護も助成対象
📌 小児慢性特定疾病医療費助成制度
対象:
18歳未満で小児慢性特定疾病に該当する方。
特徴:
- 「小児慢性特定疾病医療受給者証」で医療費負担軽減
- 訪問看護も対象
📌 障害者医療費助成制度(マル障)
対象:
重度障害者(身体障害1・2級、療育手帳A等)。
特徴:
- 自治体が医療保険自己負担を助成
- 所得制限あり
- 訪問看護も対象の場合が多い
🔄 公費負担制度と生活保護の関係
生活保護受給者であっても、上記の助成制度を利用できる場合は**まずそちらを適用する(他法他施策優先)**のが原則です。
✅ つまり、「医療券が不要」とは、「他の助成制度で全額補助される場合」を指すと考えると分かりやすいです。
✅ 公費負担制度でカバーしきれない自己負担が残った場合、医療扶助で補うために医療券が発行されるケースもあります。
📝 利用の流れの例
ここでは「指定難病受給者証」を利用する場合の流れを示します。
1️⃣ 主治医に診断書を作成してもらう
2️⃣ 市区町村に申請
3️⃣ 審査・認定
4️⃣ 「特定医療費受給者証」が交付される
5️⃣ 訪問看護ステーションに提示
6️⃣ 医療保険自己負担部分が公費負担
この場合、医療券は不要です。
💡 よくある質問
Q. 生活保護と受給者証は併用できますか?
A. 厳密には「併用する」というより、まず受給者証など他の助成制度を優先適用します。
その上で残った自己負担がある場合、医療扶助(医療券)で補う流れです。
生活保護は「最後のセーフティネット」という考え方に基づきます。
Q. 公費助成制度を使えば全額無料ですか?
A. 所得区分に応じて月額自己負担上限が定められており、全額無料ではないケースもあります。
制度ごとに負担上限が異なるため、自治体窓口で確認してください。
Q. 訪問看護ステーションはどの制度にも対応していますか?
A. 全ての訪問看護事業所が全ての助成制度に対応しているわけではありません。
利用前に事業所へ確認しましょう。
🌸 まとめ
訪問看護を利用する際、生活保護の方は原則医療券が必要ですが、他に利用できる助成制度(受給者証等)があればそちらを優先的に適用します。
✅ 医療券は「全ての助成が使えない場合の最後の支援」
✅ 他法他施策優先の原則を理解することが大切
制度は複雑で分かりにくい部分もありますが、正しく活用すれば自己負担を軽減できます。
「うちはどれが使える?」と迷ったら、主治医やケアマネジャー、市区町村窓口に相談してみてください。


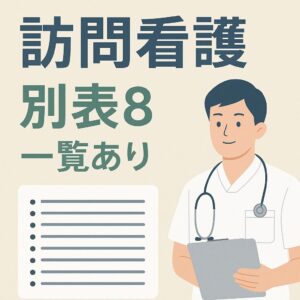



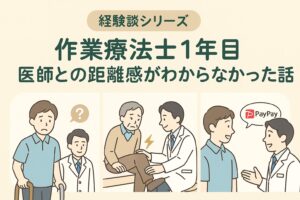

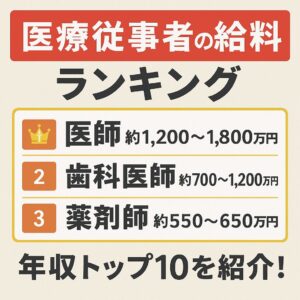
コメント