在宅で訪問看護を利用する際に、「介護保険が使えるのか?医療保険になるのか?」という判断に重要なのが、**「別表7」「別表8」**という制度です。
この記事では、医療保険で訪問看護が使えるケースを判断するための基準として定められた、別表7・別表8の内容を一覧で解説します。
Contents
別表7とは?医療保険に切り替わる「特定疾患」のリスト
要介護認定を受けていても、以下の**「別表7の疾患」に該当すれば、訪問看護は医療保険で利用可能**になります。
【別表7:対象疾患一覧】
- 末期の悪性腫瘍
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- 脊髄小脳変性症
- 進行性筋ジストロフィー症
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- ハンチントン病
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病(重度)
- 閉塞性動脈硬化症(重度)
- その他、厚生労働大臣が定める疾病
※これらに該当する方は、週4回以上の訪問や複数事業所の併用、1日複数回訪問などの特例措置が適用されます。
別表8とは?医療的管理が必要な状態のリスト
「疾患名」ではなく、「管理状態」に該当する場合が別表8です。
状態によっては、長時間訪問や高頻度の訪問看護が必要となるケースもあります。
【別表8:対象状態一覧】
- 気管カニューレの使用
- 留置カテーテルの使用
- 在宅酸素療法の実施
- 中心静脈栄養法の実施
- 真皮を越える褥瘡の存在
- 人工肛門や人工膀胱の設置
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料の算定
- その他、特別な管理が必要な状態
※別表8単独では介護保険のままですが、別表7にも該当していれば医療保険に切り替えられます。
別表7・8の活用ポイント
- 医療保険になると、訪問回数制限や限度額の縛りから外れることが多い
- ケアマネジャーではなく、主治医の判断で指示書が発行される制度
- 制度を正しく知ることで、必要なサービスが十分に受けられるかが変わる
まとめ
「別表7・別表8」は、訪問看護を医療保険で受けられるかどうかの大きな判断材料です。
疾患・状態に該当しているかどうかは、主治医との相談がカギ。
支援が必要な人に、必要な制度を届けるために、制度のしくみを理解しておきましょう。

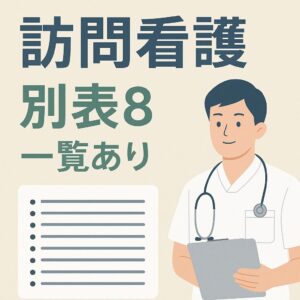





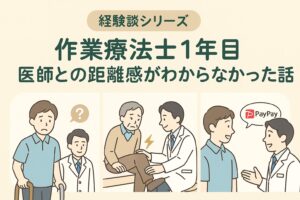

コメント